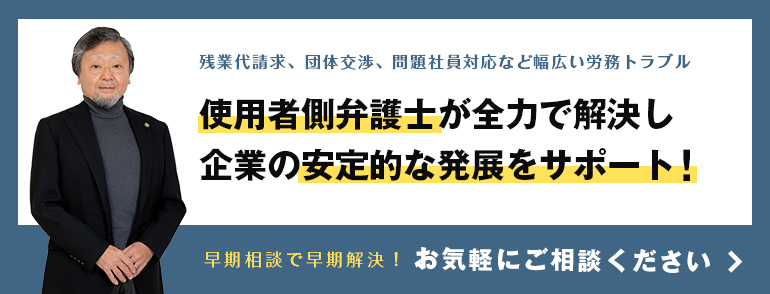- 弁護士による企業法律相談TOP
- 人事・労務 - 問題社員対応、解雇・雇止め一覧
- 休職復職を繰り返す社員
休職復職を繰り返す社員メンタル疾病に対する適切な対処法
- 精神的疾患を理由に休職している社員が、休職期間満了直前に「治癒」を理由に復職し、一定期間経過するとまた精神的疾患を理由に休職するといったことを繰り返す社員がいます。
- 休職期間に上限を設け、上限を超えて復帰できなかった場合は雇用契約が自然終了する旨の規定を置くことが当然必要となります。
- 会社としては、休業期間中、当該社員に治療に専念させ、経過報告を得ながら、主治医・産業医・家族と連絡をとり、復職のためのリハビリ勤務等、復職への道筋をつけ、症状の治癒があるかどうか慎重に見極め、治癒すれば仕事に復帰させ、短期間で治癒するという状態であれば、当座は軽易な事務につかせ、治癒を待って完全復帰させるべきです。
- こうしたフォローがないまま、杓子定規に、休業期間満了するも治癒していないので、契約終了または解雇とした場合、裁判で、要件未達または解雇権の濫用ありとして、雇用契約は終了していないとされてしまう可能性があります。
- 傷病休職において、休職事由の消滅が認められるためには、原則として従前の職務(原職)を支障なく行うことができる状態に回復したことが必要とされますが、職種や業務内容を限定していない場合、会社は、原職への就労は無理でも他に従事できる業務があるか否か、実際に配置することが可能であるかなどを考慮することが求められ、それを行わず、契約終了または解雇することは許されません。
- 復職を認めるか休職規定・復職規定の悪用ともいうべき事態を防ぐには、まず、安易に復職を認めないこと、休職期間を通算する規定を設けることが重要です。
休職規定
「休職」とは、社員に就労させることが適切でない場合に、労働契約関係そのものは存続させながら、会社が業務命令として就労を禁止することをいいます。労働者が労働を提供できないのですから、本来解雇されても仕方がないところ、一定期間解雇を猶予し、治療に専念してもらおうというのが休職制度です。
休職には、傷病休職、事故欠勤休職、起訴休職、出向休職、自己都合休職、組合専従休職などがあります。本件では、最近とくに問題になっている、精神疾患を理由とする傷病休職について、以下述べることとします。
休職制度は、就業規則や労働協約等によって定められ、休職期間の長さ、休職期間中の賃金の取扱いなどは企業によって多種多様です。近年、休職・復職をめぐる紛争が多く、規定を充実する必要もあることから、就業規則から独立させ、休職規定として独立させた方がいいでしょう。
休職命令
「社員が、私傷病を原因として、本規則による休業を申し出た場合、会社は休業を命ずることができる。」と規定される場合が多いのですが、明らかに精神疾患にかかっている場合でも、本人に病識がなく、本人からの申出が期待できないこともあるため、「業務外の精神または身体上の疾患により完全な労務提供ができないとき」にも、会社は休職命令をなしうるとすることも検討してください。
ただ、休職命令は、社員にとっては不利益処分になるため、命ずるだけの相応の理由が必要になります。このため、就業規則に産業医ないし指定医の診断を受けるように命じる受診命令を定めておく必要があります。
また会社によっては「傷病または事故により、●日をこえて引続き欠勤するとき。」として、目安を設けている場合があります。
休職期間
「傷病休職の期間の上限は、勤続●年未満の社員については●年●ヶ月、勤続●年以上●年未満の社員については●年●ヶ月、●年以上の社員については●年●ヶ月とする。ただし、会社が必要と認めた場合には、休職期間を延長することがある。」といったように、勤続年数に応じて期間の長短を分ける規定が一般的でしょう。
これは、一定期間解雇を猶予するという制度であるため、それまでの功績に応じて、猶予期間を変えていこうという発想に基づいています。
復職
厚労省のモデル就業規則では「休職期間中に休職事由が消滅したときは、原則として元の職務に復帰させる。ただし、元の職務に復帰させることが困難又は不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。」と簡易に規定されています。
ただ、復職については、(1)当該社員が、休職事由が消滅した旨を会社に届け出、(2)復職を希望する場合は、医師の診断書を提出し、(3)会社が診断書の内容に不足ないし疑問を感じた場合は、社員に産業医の診断を命ずることがあり、社員はこれに従う義務があり、(4)会社が主治医に面談を求めることもあり、この場合社員は協力しなければならず、(5)復職は、医師の診断書、産業医の意見等に基づき会社が決定し、(6)その結果として復職を適当と認めるときは復職命令を発し、(7)復職が適切でないと認めるときは、復職不許可を通知するといった手順を踏むことが必要なため、こうした手順を規定に落とし込んでいくことが必要になります。
また、復職後の業務については、原則として元の職務に復職させることになりますが、既に別の社員がその業務についている等会社側の事情により、休職前の職務に復職させることができないことがあります。その場合に、他の職務に配置する必要がありますし、後述のごとく軽易な業務で慣らし運転してもらう必要があることもあります。そのため、会社にこうした他の業務への配転命令を認め、社員は正当な理由なくこれを拒むことはできないと規定するのが良いでしょう。
通算規定
「欠勤後一旦出勤して6ヶ月以内または、同一ないし類似の事由により再び欠勤するときは、欠勤期間は中断せずに、その期間を前後通算する。」という通算規定を設けることがあります。これは、長年休職と復職を繰り返し、1年の半分しか出勤しないという問題社員が増え、社会的にも問題となったため、こうした規定が設けられました。
休職規定を新たに設けることは、給料が貰えない、勤続年数が止まってしまうという不利益的な側面もなくはないのですが、法的には一定期間解雇を猶予し、治療に専念させるという恩恵的な制度であり、近年のメンタルヘルス対策の点からも、不利益変更とは考えられてはいません。
それでは、通算規定を新たに設けることが、就業規則の不利益変更に当たらないかが問題となります。野村総合研究所事件判決(東京地判平20.12.19)は「近時いわゆるメンタルヘルス等により欠勤する者が急増し、これらは通常の怪我や疾病と異なり、一旦症状が回復しても再発することが多いことは被告の主張するとおりであり、現実にもこれらにより傷病欠勤を繰り返す者が出ていることも認められるから、このような事態に対応する規定を設ける必要があったことは否定できない。」として、「この改定は、必要性及び合理性を有するものであり、就業規則の変更として有効である。」としました。
ただ、こうした規定を設けても、1年半近く休職し、復職して6ヶ月経った直後に休職するといったことを繰り返す社員がでてくるのは防げません。では「6ヶ月」を「1年」に替えたらどうか、さらに「2年ならどうか」という議論もありうると思います。
ただ、例えば、一度うつ病で休職し、復職し6ヶ月後にうつ病を発症した場合、「じゃあ前のうつ病も完治していなかったんじゃないか。復職を認めるべきではなかった。」と考えられるからこそ、前後の休職期間を通算することもありうるでしょう。しかし、それが数年後の発症ということになれば、完治してからの発症というべきでしょう。病名は同一でも、同一の精神疾患とはいえないでしょう。
そうすると、6ヶ月にすべきか、1年にすべきか、それとも3年かというのは、医学的知見も含めて検討すべき問題のように思います。
現状は、上記判決が認めた「6ヶ月」を超えた発症を前回の休職期間と通算しないことは認めるとしながら、「前のときは6ヶ月後少しで再発したのだから、完治していなかったのではないか」と主張し、次の復職の際は、本当に完治しているのかどうか、主治医、産業医も交えて慎重に検討するのが無難でしょう。
自然終了規定
(1)休職期間が満了しても休職事由が消滅しないときは、休職期間の満了をもって退職とすること、(2)休職期間が満了し、出社できる状態になっているにもかかわらず、正当な理由なく会社が指定した日に出社しなかった場合は、その翌日をもって自動退職とすることを就業規則に規定します。
規則によっては、解雇すると規定しているものもありますが、解雇となると、(1)解雇権濫用法理が適用になること、(2)解雇の意思表示が必要になり、機を失することもありうることを考えると、上記のように自然退職とした方がいいでしょう。
厚労省のモデル就業規則も「自然退職」としています。
休職中の取り扱い
給与
休業中の取り扱いで、重要なのは給与を支給するかです。ノーワークノーペイの原則からして、休業期間中に給与を支払う必要はありません。また、私傷病(労災によらない傷病のこと)の場合は、健康保険組合から傷病手当が出ますので、当該社員の生活は最低限同手当によって賄うことができます。
職場復帰支援
厚労省が作成した「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」に基づき、休職中の社員が円滑に職場復帰できるよう、職場復帰プログラムの策定や関連規程の整備をし、休業から復職までの流れをあらかじめ明確にし、この流れにそって粛々と手順を踏む必要があります。
社長さんの中には「あいつは仮病だ、仮病して怠けている人間に、何でそこまでしてやる必要があるんだ。」とい疑問をお持ちの方もいると思います。しかし、問題社員対応は、全て、同じスタンスのもとに行われなければなりません。それは「問題社員だからとって、指導を放棄することはできない。問題社員だからこそ、(少なくとも建前上は)改善を促すため、指導をし、研修をし、場合によっては配転し、別の適性がないか確認するという努力を尽くし、ここまで努力したのに改善しないんです。もう打つ手がないんです。」と主張して初めて、裁判所は解雇を認めてくれるのです。
休職と復職を繰り返す社員に対しても、同様に対応する必要があるのです。「一応本人が、うつ病だというし、医師の診断書も出ているから、うつ病として扱うほかない。彼がうつ病だという前提で、症状を定期的に把握し、主治医からも症状を聞取り、また会社からの当該社員の職務内容を伝え、会社・産業医・家族とで情報を共有し、協力し合いながら、職場復帰までの道を整えていくのです。
会社としては、リハビリ通勤(会社に通わせるが、仕事はさせない。)等、復職への心理的ハードルを少しずつ下げて行く必要があり、復職後の業務内容等も伝え、心理的負担を下げていくことが重要です。
具体的手順については、前述の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」の改訂版を参考にしてください。ネットで見ることができますし、プリントアウトし、保管しておいたほうが良いでしょう。
復職ないし復職不許可までの手順
判断するのはあくまで会社
復職を判断するのは、あくまで会社です。会社が、復職を認めず、そのまま休職期間を満了した場合は、契約終了又は解雇となるため、社員側から裁判で争われることもありえるため、そうなることも想定した上で対処する必要があります。
受診命令
復職の手続きは、休職者が会社に対して復職を希望する旨申出るところから始まり、当然、主治医の診断書も提出してもらう必要があります。主治医は、患者の意向を過度に尊重して診断書を書くことが珍しくありません。
そのため、必要に応じて会社の指定する医療機関または産業医の診断を命ずることがありますが、そのためには、就業規則に、受診命令を規定する必要がありますし、社員はこれを拒むことはできない旨を規定する必要があります。また、会社の人間が主治医に面談を求められたら、社員はこれに協力しなければならない旨を規定する必要があります。
復職命令
会社が「治癒した」と認めた場合は、社員に復職を命ずることになりますが、逆に、「治癒した」とは認められず、復職が適切でないと認める場合は、復職不許可を社員に通知することになります。
復職にともなう配置転換
原則として元の職務に復職させますが、休職中に社員がいたポストに別の人間がついているケース、しばらくは軽易な作業をさせ、様子をみる必要があるケースもあるため、そうした場合、他の職務に配置することができる旨、従業員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない旨を規定しておく必要があります。
自然退職ないし解雇
治癒しないまま、休職期間が満了した場合は、休職期間の満了をもって自然退職となるか、解雇となります(そのどちらかになるかは就業規則による)。休職期間が満了し、出社できる状態になっているにもかかわらず、出社してこない場合もあるため、その場合は、会社が期日を定めて出社を命じ、その期日に出社してこなければ翌日をもって自然退職とする旨規定する必要があります。
治癒
治癒とは
傷病休職は、休職期間内に治癒し就労可能となれば、休職は終了し、会社は復職を命ずることになります。逆に、治癒しないまま休職期間が満了すれば復職できず、就業規則に従い、自然退職ないし解雇を検討することになります。そのため、治癒の判断が非常に重要となるのです。
社員との面接
社員に面接し、職場復帰に対する意思を確認します。社員に復職の意思がなければ、退職に向けた手続きに入ります。社員に復職の意思があれば、社員に対して、(1)主治医の意見も尊重するが、最終的に職場復帰を決めるのは会社であり、(2)産業医の意見を聞き、現場の受け入れ体制も配慮した上で、その結果を通知すること、(3)取り敢えずは主治医とも面接する必要があるので、主治医にもその旨伝えてくれるよう伝えます。
主治医との面接
医師は守秘義務を負っており、本人の承諾がないと、患者についての情報を伝えることができません(同意なしに情報を伝えることは秘密漏洩罪という犯罪になります。)。
本人が承諾してくれれば良いのですが、拒否する場合は、拒否する理由も聞き、また、今回の聴取は職場復帰できるかどうかを判断する材料を得るため、最低限必要な情報を得るためのものであることを説明し、極力説得に努めてください。こうした交渉の記録は残すようにしてください。)は、当該社員を通じ、主治医に対し、復職可能と判断した根拠となる資料の提示を求めることになります。
主治医との面談では、治癒の程度に関する情報、判断の根拠の徴収し、職場復帰支援に関する社内制度を説明しますが、一番重要なのは、主治医に「職場で必要とされる業務遂行能力」を説明することです。主治医と情報交換を行う場合、当該社員本人の職場復帰を支援する立場を基本とし、そこで得る情報は職場で配慮すべき事項を中心に必要最小限のものとします。その際、次項で述べる「職場復帰可否の判断基準」を意識して情報交換を行ってください。
復帰に不安を感じる場合は、別項で述べる「試し出勤制度」を提案するなどして、主治医との連携を深めるのもいいでしょう。当該社員の治癒の否定材料を探していると捉えられては、主治医と対立を有無だけで、百害あって一理もありません。そうならないためにも、休職期間中の主治医との信頼関係の醸成が必要になるのです。
受診命令
就業規則で「社員から診断書が提出された場合でも、会社は、会社の指定する医師への検診を命ずることがあり、社員は同命令に従わなければならない。」として規定しておくべきでしょう。
当該社員がこれに従わないこともありえます。確かに、主治医は、医学的見地から、治癒したかどうかを判断できるでしょうが、復職で要求される「治癒」は「従前の職務を通常の程度に行える健康状態に復した」かどうかであり、判断基準にもおのれとズレがあります。後者の観点から、「治癒」がなされたかどうかは、主治医との面接を通し、その点を判断することもある程度可能ですが、産業医(又は会社指定医)が主治医の判断に疑問を持った場合、なお、産業医の診断結果を得ないままでは「治癒」したかどうかについて、十分な判断ができません。
そもそも「治癒」したかどうかについて証明責任を負うのは、社員側ですから、主治医の診断書の信用性が否定され、証明不十分として、治癒はしていないとの会社の主張が認められる可能性も十分あります。
なお、当時の電電公社が、頸肩腕症候群の症状がある職員に対して精密検査を受けるよう命じたが、職員がこれを拒否したので戒告処分にしたところ、職員が同処分の有効性を争った事案において「公社が被上告人の右疾病の治癒回復のため、頸肩腕症候群に関する総合精密検診を受けるようにとの指示をした場合、被上告人としては、右検診について被上告人の右疾病の治癒回復という目的との関係で合理性ないし相当性が肯定し得るかぎり、労働契約上右の指示に従う義務を負っている(電電公社帯広局事件・最判昭61.3.13)」と判決し、受診命令の有効性を認めています。
職場復帰可否の判断基準
職場復帰の可否の判断基準には次のようなものがあります。
- 本人が十分な意欲を示している。
- 通勤時間帯に一人で安全に通勤ができる。
- 決まった勤務日、時間に継続して就労できる。
- 業務に必要な作業ができる。
- 作業による疲労が翌日までに十分回復する。
- 適切に睡眠覚醒リズムが整っている。昼に眠気がない。
- 業務遂行に必要な注意力・集中力が回復している。
試し出勤制度(リハビリ出勤制度)
正式な職場復帰決定前に、社内制度として、次のような試し出勤制度等を設け、より円滑な職場復帰が可能になります。また、これを実施することで、その時点での治癒状況がより正確に把握できます。(1)(2)の出勤は、労働を伴うものではないため、ノーワークノーペイの原則に従い、給料が発生しないことを就業規則に明示した方が良いでしょう。
- 模擬出勤:勤務時間と同様の時間帯にデイケアなどで模擬的な軽作業を行ったり、図書館などで時間を過ごす。
- 通勤訓練:自宅から勤務先の近くまで通勤経路で移動し、職場付近で一定時間過ごした後に帰宅する。
- 試し出勤:職場復帰の判断等を目的として、本来の職場などに試験的に一定期間継続して出勤する。但し、仕事はさせません。
試し出勤では、限定的に休職を解除し、一時的に会社業務を行わせ、治癒の程度を観察し、人事考課をし、その結果も踏まえて、産業医により休職に戻すかどうか、再検討することも考えられます。
産業医の判断と主治医の判断
主治医の判断と産業医の判断とが対立したまま、会社が産業医の判断にしたがって復職を認めず、結果、自然退職ないし解雇となり、裁判となった場合、どちらの判断に従った判決がなされるのでしょうか。
復職後の配属
雇用契約の中で従業員の職務が限定されている社員については、従前の職務を遂行することが可能な程度に回復していない場合には、復職可能状態にあるとは認められず、社員側で就労可能な範囲で働きたい旨希望したとしても、会社には、これを受領する義務はなく、また、社員の希望に見合う業務を見つけなければならない義務もありません。
ただ、この場合も、長距離トラック運転手として採用された者につき、復職後短距離トラック運転手としては仕事ができるのであれば、復職を認めず自然退職とした会社の処分を無効とした判例もあるので注意が必要です(カントラ事件・大阪高判平14.6.19)。また、当初は軽易な作業にしかつけなくても、短期間で従前の仕事に復帰できるの場合は、自然退職とはならないと判断される可能性も十分ありえます。
しかし、雇用契約の中で従業員の職務が限定されていない社員の場合、以前従事していた仕事にはつけないとしても、能力、経験、地位、会社の規模、業種、会社における従業員の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該社員が配置される現実的可能性があると認められる他の仕事ができるのであれば、裁判所において「治癒」したと判断される可能性があります(片山組事件・最判平10.4.9)。
問題社員対応には弁護士のサポートが必要です
問題社員の対応を怠ってしまうと、問題社員との関係はもちろんですが、最大の問題は、周囲の社員のモチベーションを下げ、労働生産性を下げてしまうリスクばかりでなく、最悪の場合、会社に嫌気がさして辞めてしまうという可能性があることです。
多くの経営者は、なんとかしたい、ただ、対応するエネルギーがない、法律的にどういった対応がベストなのかわからない。といった悩みを抱えているのではないでしょうか。
問題社員の対応は、注意指導、配置転換・降格、懲戒処分、退職勧奨、解雇など法律的に適切なプロセスを踏んで対応していかなければなりません。その対応を間違えれば、企業にとって大きなリスクになります。そのため、人事労務問題を熟知した弁護士のサポートが必要なのです。
当事務所では、労働問題に特化した顧問契約をご用意しております。法改正対策はもちろん、労働時間管理やフレックスタイムの導入や、問題社員対応、人材定着のための人事制度構築など、企業に寄り添った顧問弁護士を是非ご活用ください。
問題社員対応 メニュー
- 問題社員対応編
- 問題社員に対する指導
- 勤務態度が悪いモンスター社員
- 能力不足・成績不良社員
- 職務怠慢な社員を辞めさせたい
- 協調性の欠如を理由とする解雇
- 休職復職を繰り返す社員
- 従業員が会社のお金を横領した
- 問題社員を解雇する際の留意点
- 配置転換における対処法
- 試用期間による対処法
- 内定取り消しによる対処法
- 管理職の能力不足
解雇・雇止め メニュー
人事・労務 メニュー