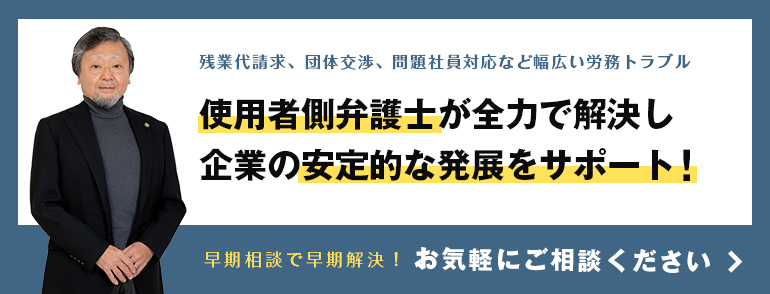- 弁護士による企業法律相談TOP
- 残業代請求・未払い賃金
- 管理職は管理監督者?
管理職は管理監督者?有名判例に見る適切な対処
管理職は、残業代は必要ないとよく言われていますが、会社内で管理職としての地位にある社員でも、労基法上の「監督若しくは管理の地位にある者」(41条2号)である管理監督者に当たらないことがあります。そのため、権限も与えられず、ふさわしい賃金上の処遇が与えられていないまま肩書だけを「課長」にしたとしても、残業手当を支払わなくて良いということにはならないのです。
管理職であれば、何時間働いても構わないと誤解されることも多々ありますが、「管理監督者」であっても健康を害するような長時間労働をさせてはいけないのです。
管理監督者に法律上の労働時間規制が及ばないのは、管理監督者が事業主に代わって労務管理を行う地位にあり、従業員の労働時間を決定し、その業務を監督する者だからです。他の従業員の労働時間を管理・監督する権限を持っている以上、自らの労働時間は他の者には管理されず、自らの裁量で決めることができるため、労働時間規制を適用することは不適当なのです。
また、管理監督者は、その職務の重要性から、地位、給料その他の待遇において一般社員と比較して相応の待遇がなされているため、労働時間規制を適用しないことに不都合はないということなのです。
なお、管理監督者であっても、深夜労働に対する割増賃金支払義務が免ぜられることはありません(ことぶき事件、最判平成21年12月18日労判1000号5頁)。
管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的地位にある者をいい、名称にとらわれず、職務内容、責任と権限、勤務態様、待遇を踏まえて実態に即して判断されます。
具体的には、以下の判断基準が用いられています。
- 当該労働者が実質的に経営者と一体的な立場にあるといえるだけの重要な職務と責任、権限を付与されているか
- 自己の裁量で労働時間を管理することが許容されているか
- 給与等に照らし管理監督者としての地位や職責にふさわしい待遇がなされているか
そのため、残業代請求事件において、管理職が管理監督者か否かが争われるケースの場合、審理のポイントとなるのは以下であると考えられています。
- 当該対象者に、管理職手当ないし役職手当等の特別手当が支給されていること。そして、その手当と時間外労働の時間等との関連の有無。
- 対象者の出退勤についての規制の有無ないしその程度。
- その職務の内容が、ある部門全体の統括的な立場にあるか否か。
- 部下に対する労務管理上の決定権等について一定の裁量権を有しているか。部下に対する人事考課、機密事項に接しているか否か。
コナミスポーツクラブ事件
コナミスポーツクラブ事件(東京地判平成29年10月6日労経速2335号3頁)は、支店長として務め、マネージャーに降格した者が、時間外労働、休日労働および深夜割増賃金を請求した事件で、管理監督者性が争われました。
この裁判例では、「支店長として比較的柔軟に出勤時刻を調整して、中番や遅番で出勤していたことがうかがわれる」ものの、これは、「支店の一般の従業員がシフト制で勤務をしていたために、特定の時間帯の人員が不足する場合や、閉店作業を行う従業員が他にいない場合に、支店長の勤務時間を調整して対応していたことによるものでしかなかった」として(2)自己の裁量で労働時間を管理することが許容されているかについて、否定しました。
この裁判例では、(1)(3)の判断も否定されたため、管理監督者であるとは認められませんでした。
上記審理のポイントや裁判例を見ても分かるように管理監督者であると認められるハードルは高い傾向にあり、裁判例では否定されることが圧倒的に多いです。
裁判例一覧
| 事件名 | 役職名 | 判断事由 | 管理監督者 |
|---|---|---|---|
| レストラン「ビュッフェ」事件(大阪地裁) | 店長 |
|
× |
| 彌英自動車事件(京都地裁) | 係長補佐、係長 |
|
× |
| リゾートトラスト事件(大阪地裁) | 係長 |
|
× |
| 日本コンベンションサービス事件(大阪高裁) | 参事、係長、係長補佐等のマネージャー職 |
|
× |
| 医療法人徳洲会事件(大阪地裁) | 人事第二課長 |
|
○ |
| セントラルスポーツ事件(京都地裁) | エリアディレクター |
|
○ |
その他の裁判事例
認められなかった例
- 国民金融公庫事件……地位:業務役(支店)
- ほるぷ事件……地位:販売主任(支店)
- キャスコ事件……地位:主任(支店)
- 東建ジオテック事件……地位:次長、課長、課長補佐、係長(支店)
- 育英舎事件……地位:営業課長(本部)
認められた例
- アント・キャピタル・パートナーズ事件……地位:パートナー社員
- INSOU西日本事件……地位:取締役・管理本部長
- VESTA事件……地位:営業部門責任者
もっとも、最近の裁判例の傾向として、職務内容、権限及び責任に照らし、労務管理を含め、企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているかが着目要素とされ、企業全体の事業経営に関する重要事項への関与という形で強調されるようになる反面、その一方で、企業全体の事業経営に関する重要事項へのアクセス等を特に考慮要素に挙げない裁判例もあり、必ずしも統一的な判断枠組みが定立・維持されているとは言えません。
会社としては、管理職が管理監督者に該当するか否かを検討する前提として、管理職の職務内容や待遇、管理職の従業員に占める割合などを客観的に把握することが必要です。
そのため、①職務内容、権限、責任に関する資料(雇用契約書、組織表、職務範囲等を決めた文書など)、②勤務態様に関する資料(雇用契約書、就業規則、タイムカード、シフト表など)、③待遇に関する資料(雇用契約書、賃金規程、賃金台帳など)といった客観的な資料によって把握し、説明できるようにしておくことが大変重要となってきます。
会社によって組織や規制は様々ですから、上記判断基準に当てはまるかどうか一律の基準で判断することはできません。個別具体的に管理監督者に当てはまるかどうかについて考えなければなりませんので、専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
また、管理職の場合、労働時間がかなりの時間になっている可能性も非常に高く、残業代請求をされ、管理監督者性が否定されてしまうと、会社が負担すべき支払額が高額になりかねませんので、日ごろから弁護士などの専門家による助言、支援を受けることを強くお勧めします。
労務管理には弁護士のサポートが必要です
労務管理を行うためには、多岐にわたる法律に知っておく必要であり、昨今、労働法規は、法改正が立て続けに行われています。法律を「知らなかった」「きちんと運用出来ていると思っていた」では済まされず、特に、残業代請求に対する対応は、その運用を間違えれば、数百万円単位の支払いを求められ、企業にとって大きなリスクになります。そのため、労働問題を熟知した弁護士のサポートを受けながら、制度を構築・運用していくことをお勧めします。
当事務所では、労働問題に特化した顧問契約をご用意しております。経営に専念できる環境整備はもちろんですが、予防法務、制度構築運用など、企業に寄り添った顧問弁護士を是非ご活用ください。
残業代対応の予備知識 メニュー
残業代請求対応方法について メニュー
人事・労務 メニュー