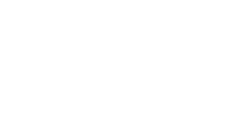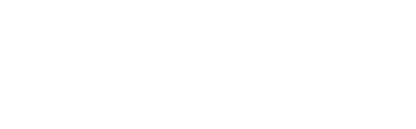- B型肝炎給付金請求TOP
- B型肝炎について
- 献血をしてB型肝炎の通知が来たらどうすればいい?
献血をしてB型肝炎の通知が来たらどうすればいい?
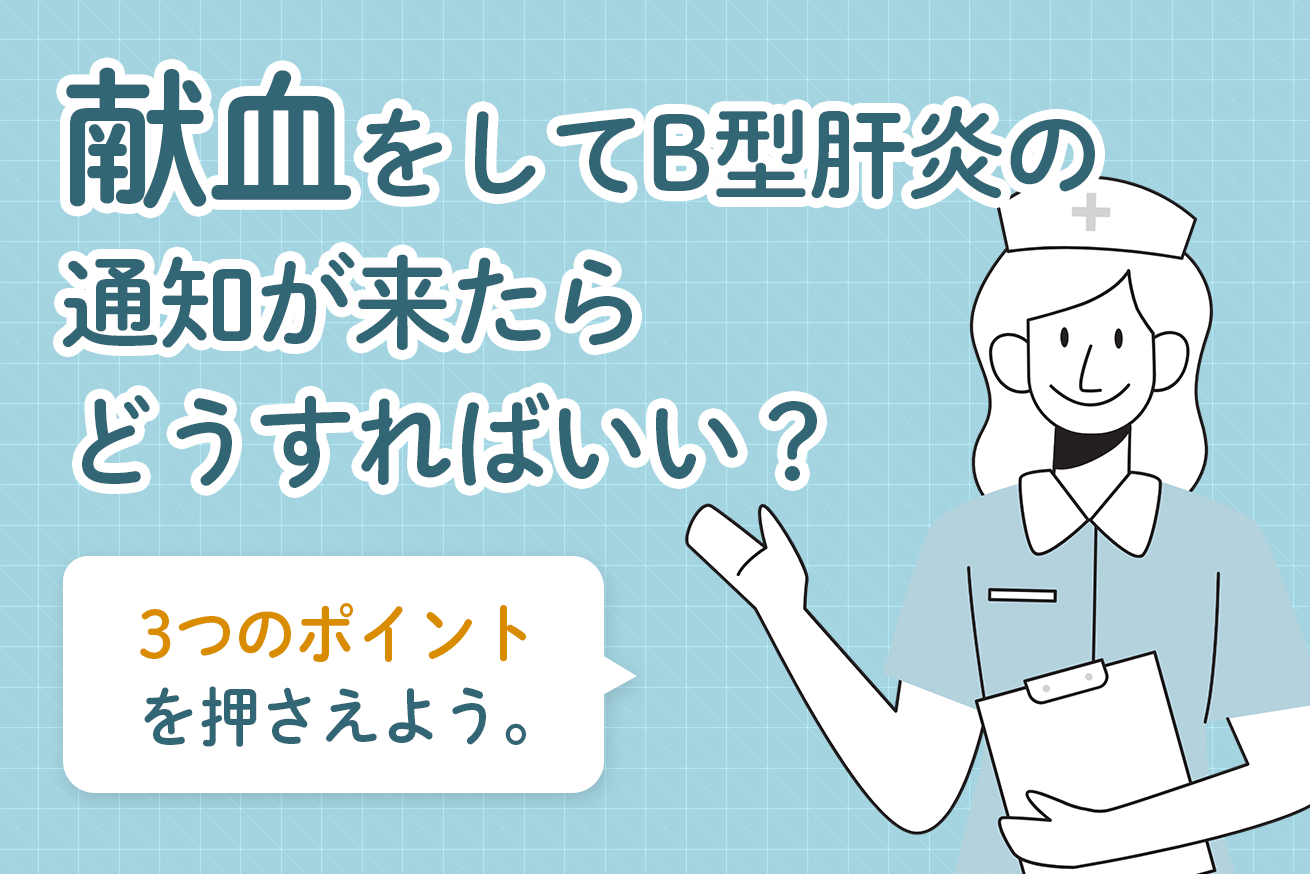
目次
献血をした結果、感染症検査に異常がみられると、日本赤十字社から封書でお知らせが届きます。この通知でB型肝炎ウイルスへの感染を知る方は非常に多く、同時に、突然のことで戸惑い、不安を感じたという話しをよくうかがいます。ここでは、そのような方に向けて、B型肝炎の基礎知識や、通知を受け取った後どうすればよいのか等について解説します。
なぜ、献血でB型肝炎とわかるのか?
献血とは、病気や怪我の治療で、輸血などが必要となった方のために、健康な人が自ら血液を提供するものです。そのため、提供された血液に病原体が混ざりこんでいないかどうかを確認するために、感染症検査を行っています。
その検査項目の中に「B型肝炎ウイルス検査」も含まれているため、献血で知る方がいるのです。
なお、献血で実施している感染症検査は以下の通りです。
- B型肝炎ウイルス検査
- C型肝炎ウイルス検査
- E型肝炎ウイルス検査
- 梅毒トレポネーマ検査
- エイズウイルス検査
- ヒトT細胞白血病ウイルス検査
- ヒトパルボウイルスB19検査
献血で行なっているB型肝炎ウイルス検査について
実際、献血のときに行なっているB型肝炎ウイルス検査項目は以下の4つになります。
- HBs抗原検査
- HBs抗体検査
- HBV-DNA検査
- HBc抗体検査
(1) HBs抗原検査
B型肝炎ウイルスに感染しているかどうか調べる検査で、陽性の場合は、現在、B型肝炎ウイルスに感染している状態となります。
(2) HBs抗体検査
過去にB型肝炎ウイルスに感染したことがあるかどうかを調べる検査で、陽性の場合は、以前にB型肝炎ウイルスに感染していたことがある、ということです。
また、B型肝炎ワクチンを接種した場合も陽性となります。
(3) HBV-DNA検査
B型肝炎ウイルスへの感染の有無やウイルス量などを調べる検査で、陽性の場合は、現在、B型肝炎ウイルスに感染している、ということです。陰性の場合は「検出せず」という結果となります。
(4) HBc抗体検査
B型肝炎ウイルスに現在感染しているか、または、過去に感染したことがあるかどうかを確認する検査です。陽性・低力価(10.0S/CO未満)の場合は過去に感染したことがある、陽性・高力価(10.0S/CO以上)の場合は、現在B型肝炎ウイルスに感染している、ということになります。
持続感染と一過性感染について
B型肝炎ウイルスは、感染した場合、ほとんどは一時的な感染(一過性感染)で済みます。その理由は、何かの原因でB型肝炎ウイルスに感染し、体内にウイルスが入ったとしても、自己免疫機能が作用し、ほとんどの場合、約3~6か月の間にウイルスは体外に排出され、自然治癒した状態になります。これを一過性感染といいます。
献血時に行なう血液検査結果でいうと、「HBs抗原やHBV-DNAは陰性、HBs抗体やHBc抗体検査陽性」の方がこれに該当します。
しかし、免疫機能が未発達である幼少期にB型肝炎ウイルスに感染してしまうと、ウイルスが体内に入ってきたとしても、ウイルスを異物として判断できず、体外に排出することができないため、ウイルスが体内に残り続けてしまう状態となります。これを持続感染といいます。
また、B型肝炎ウイルスのなかには、成人してから感染しても持続感染するウイルス(ジェノタイプAe)もいます。
持続感染者の場合、血液検査結果でいうと、「HBs抗原やHBV-DNA陽性」の方がこれに該当します。
一方、一過性感染を示す結果(HBs抗原やHBV-DNAは陰性、HBs抗体やHBc抗体は陽性)の場合、手続きの対象はならない可能性が高いといえます。(HBc抗体の数値によっては、持続感染と判断される可能性はあります)
献血の結果通知の2つのパターン
献血を行なった結果、B型肝炎だとわかった場合、日本赤十字社から通知が届きます。その内容は、検査結果によって、主に以下の2パターンがあります。
- 現在、B型肝炎ウイルスに感染している可能性が高い状態
- 過去にB型肝炎ウイルスに感染したことがあるが、現在は治っている状態
そのほか「偽陽性」という通知が届くことあります。この場合、B型肝炎に感染しているわけではありませんが、以降の献血はできなくなります。
(1) 現在、B型肝炎ウイルスに感染している可能性が高い状態
B型肝炎ウイルスに感染している可能性が高い方の場合、血液検査結果のうち、HBs抗原やHBV-DNAが陽性になっています。
これは、現在、B型肝炎ウイルスが体内にある、ということを示していますので、B型肝炎ウイルスに持続感染している可能性が高いといえるため、日本赤十字社からの通知にも、受診を勧める内容の記述があります。
(2) 過去にB型肝炎ウイルスに感染したことがあるが、現在は治っている状態
日本赤十字社の通知では、B型肝炎ウイルスに過去に感染したことがあるという方の場合、血液検査結果は、HBs抗原やHBV-DNAは陰性、HBs抗体やHBc抗体が陽性となっています。この場合、B型肝炎ウイルス(抗原)は陽性判定未満であり、すでに抗体を獲得していることから、日本赤十字社では、すでに自然治癒している状態として一過性感染と判断しています。
ただ、日本赤十字社から一過性感染と判断されたからといって、B型肝炎給付金の対象者とならないということではありません。B型肝炎給付金では、HBc抗体の数値によっては、持続感染と判断される可能性があります。日本赤十字社からの通知には、HBc抗体の数値まで記載されていないため、ご自身が対象かどうか調べるには、さらに数値を確認することが必要となります。
献血の結果、B型肝炎とわかった場合はどうすればいい?
(1) 現在、B型肝炎ウイルスに感染していることがわかったら
1. 肝疾患専門医療機関を受診する
日本赤十字社から通知が届き、B型肝炎ウイルスに感染している可能性があることが判ったら、まず肝疾患専門医療機関を受診しましょう。
肝臓は「沈黙の臓器」と言われており、自覚症状がなくても、慢性肝炎などを発症している可能性があります。
2. 都道府県から検査費用などの助成を受けられるか確認する
B型肝炎に関する検査費用や治療費について、条件を満たしていれば、都道府県から以下のような助成を受けることができる可能性があります。
- 肝炎初回精密検査費用助成
- 定期検査費用助成
- 肝炎治療医療費助成
詳しくは、以下のページをご覧ください。
3. B型肝炎給付金の対象となるかどうかを確認する
B型肝炎ウイルスに持続感染した原因が、幼少期に受けた集団予防接種等による注射器などの連続使用によるものであれば、病態により、50~3600万円の給付金を受け取ることができます。
給付金を受け取るには、要件を満たす書類を収集し、国を相手に裁判を起こす必要があります。まずは、対象となるかどうかを確認するためにも、弁護士に相談することをおすすめします。
(2) 過去にB型肝炎ウイルスに感染していたことがわかったら
1. 受診の際は、B型肝炎ウイルスに既感染していたことを伝える。
血液検査結果から、HBs抗原やHBV-DNAが陰性、HBc抗体陽性の場合、一過性感染となり、自然治癒したと判断されます。
ただ、B型肝炎ウイルスは、自然治癒したとしても、体内(特に肝臓)にはごく僅かのウイルスが残っています。
抗がん剤やリュウマチ治療薬などの治療薬を使用することにより、ウイルスが増えてしまうこともあります(ウイルスの再活性化といいます)。
そのため、病院を受診する際には、問診票の既往歴(今までにかかった病気)に記入する等して、B型肝炎に感染したことがあると伝えるほうが良いでしょう。
2. B型肝炎給付金の対象者となるか確認する
B型肝炎給付金の対象となるのは、B型肝炎ウイルスに持続感染していることであるため、原則として一過性感染の場合は手続きの対象外となります。
ただ、日本赤十字社からの通知には、HBc抗体検査の結果(陽性・陰性)は記載されているものの、数値まで記載されておりません。
持続感染とは、HBs抗原(HBe抗原、HBV-DNAを含む)が6か月以上空けた2時点で陽性であるか、HBc抗体陽性かつ高力価であることとされており、HBc抗体検査の数値によっては、持続感染と判断される可能性はありますので、日本赤十字社に連絡し、HBc抗体の数値を確認するか、改めて血液検査を受けることをお勧めします。
3. 家族にB型肝炎の方がいないかどうか確認する
献血の結果、一過性感染だとわかったとしても、一度はB型肝炎ウイルスに感染した事実に変わりはなく、ご家族から感染したということも考えられます。
ご本人はB型肝炎給付金の対象外だとしても、ご家族のなかに、B型肝炎ウイルスに持続感染している方がいれば、手続きの対象となる可能性もあります。
ご家族で、過去にB型肝炎ウイルス検査を受けたことがない方がいれば、検査を受けるように勧めてみてもよいかもしれません。
【参考】献血とB型肝炎の歴史
1. 献血とB型肝炎関連検査
1952(昭和27)年に日本赤十字社が「血液銀行」を開設し、献血事業がスタートしました。しかし、当時は民間商業血液銀行による買血(ばいけつ)がさかんに行なわれており、買血による輸血から「輸血後肝炎」が社会問題になりました。
それを受け、1964(昭和39)年、政府は「輸血用血液は献血により確保する」と閣議決定し、日本赤十字社または地方公共団体による献血受入れ体制が整備されたことから、1969(昭和44)年、民間商業血液銀行は買血による輸血用血液の供給を中止しました。
1972(昭和47)年、輸血後B型肝炎予防のため、すべての献血血液について、B型肝炎ウイルス(HBs)抗原検査を開始し、さらに、1989(平成元)年には、B型肝炎ウイルス(HBs)抗原検査に加え、HBc抗体検査を開始しました。
その後、B型肝炎ウイルスに一過性感染(HBs抗原陰性、HBc抗体陽性)した方は、自身の健康に影響を及ぼすことはないものの、肝臓の中にごく微量のB型肝炎ウイルスが存在し続けており、まれに血液中にもごく微量のB型肝炎ウイルスが検出される場合があることがわかったことから、2012(平成24)年8月、検査基準を変更し、HBs抗原陽性の方だけではなく、HBc抗体陽性の方も、献血できないようになりました。
2. なぜ、献血でB型肝炎ウイルスに感染していることを知る人が多いのか?
B型肝炎ウイルスに感染したことを知るきっかけには、様々ありますが、その中でも、若いころに行なった献血で知った、という方が多くいます。
1964(昭和39)年、政府が「輸血用血液は献血により確保する」と閣議決定した当時、献血由来の輸血用血液はわずか2%しかありませんでした。そのため、今まで以上に献血を行えるように、日本赤十字社や地方自治体は、献血の受入れ体制を強化し、今まで少なかった移動採血車(献血バス)が増えたことにより、学校や会社、工場、事業所など、数多くの人が集まる場所で、集団献血ができるようになりました。その結果、後の10年間で国内自給(献血由来100%)を達成できるほどの献血する人数が増加しました。
1972(昭和47)年に、すべての献血血液について、B型肝炎ウイルス(HBs)抗原検査を開始したことにより、献血に協力した方が、B型肝炎に感染していることを知るきっかけとなりました。
さらに、B型肝炎ウイルス(HBs)の抗原検査を開始した後、1975(昭和50)年には、「第1回はたちの献血」のラジオキャンペーンが開始され、学校行事の際や卒業記念献血などと称して、若年層への献血への協力を促しました。
結果、1985(昭和60)年には、16~19歳の献血実施率は同世代人口の約25%、約180万人以上の人が献血をしたことになるため、学生時代にB型肝炎だと知る方が多くいると思われます。(現在は約4%の献血実施率)
なお、現在でも「はたちの献血キャンペーン」や学校献血などは実施されています。
同じカテゴリーの記事一覧
-
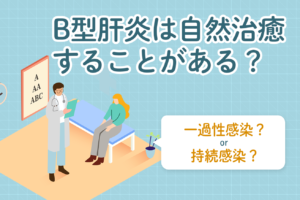 B型肝炎は自然治癒することがある?病院で血液検査をしたところ、「B型肝炎になったことがあるけど、もう治っている」と言われることがあります。ここでは、B型肝…
B型肝炎は自然治癒することがある?病院で血液検査をしたところ、「B型肝炎になったことがあるけど、もう治っている」と言われることがあります。ここでは、B型肝… -
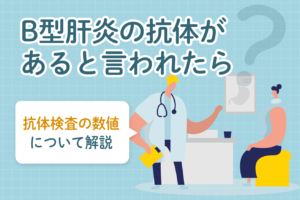 B型肝炎の抗体があると言われたらどうすればいい?抗体検査の数値について解説病院や健康診断などで血液検査を行なった結果、「B型肝炎の抗体がある」とか「過去に感染した跡がある」と言われることがありま…
B型肝炎の抗体があると言われたらどうすればいい?抗体検査の数値について解説病院や健康診断などで血液検査を行なった結果、「B型肝炎の抗体がある」とか「過去に感染した跡がある」と言われることがありま… -
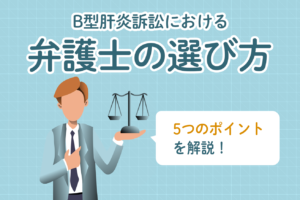
- 請求について
B型肝炎訴訟における弁護士の選び方とは?弁護士を選ぶ5つのポイントB型肝炎給付金における法律事務所(弁護士)の選び方、そのポイントについて説明していきます。 -
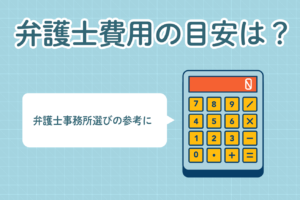
- 請求について
B型肝炎給付金で弁護士費用はどれくらいかかる?その目安とはここでは、B型肝炎訴訟の弁護士費用の仕組みと目安について説明します。弁護士費用についての知識があれば、弁護士事務所を選ぶ… -
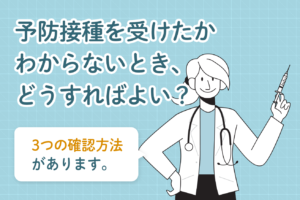
- 対象者について
B型肝炎給付金で予防接種を受けたかわからないとき、どうすればよい?B型肝炎ウイルスに持続感染していたとしても、集団予防接種等を受けていることが証明でないと給付金を受け取ることはできません… -
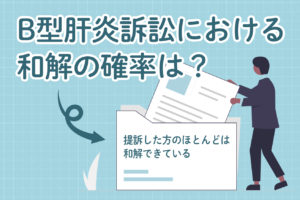
- 請求について
B型肝炎訴訟における和解の確率を知りたい。目安となる数字とは?相談者の中には、「国と和解できる確率が高いなら、手続きしてみようかな」という方がおられます。ここでは、訴訟した方のうち、… -
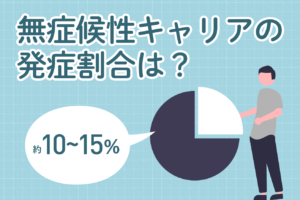
- 対象者について
B型肝炎で無症候性キャリアの場合、どれくらいが発症する?B型肝炎に持続感染していても、肝炎を発症していない方を「無症候性キャリア」といいます。ここでは、無症候性キャリアについて… -
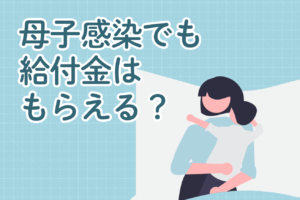
- 対象者について
B型肝炎の二次感染についてB型肝炎ウイルスが母親から感染し、母親が集団予防接種等を原因としてB型肝炎ウイルスに持続感染していた場合、二次感染者とし… -
 B型肝炎はうつる?日常生活でうつる確率と気をつけるべきことB型肝炎ウイルスは、ウイルス感染者の血液や体液に傷口や粘膜などが接触することで感染します。ここでは、日常生活でうつる確率…
B型肝炎はうつる?日常生活でうつる確率と気をつけるべきことB型肝炎ウイルスは、ウイルス感染者の血液や体液に傷口や粘膜などが接触することで感染します。ここでは、日常生活でうつる確率… -
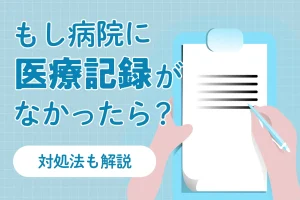
- 請求について
B型肝炎給付金請求に必要なカルテがない場合どうしたらいい?手続きに必要な医療記録(カルテや検査記録等)の説明や、医療記録などが現存していなかった場合ついて、詳しくご説明します。