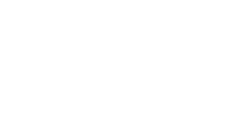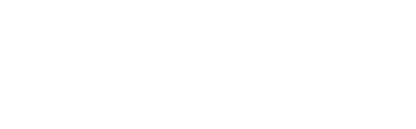- B型肝炎給付金請求TOP
- B型肝炎について
- B型肝炎はうつる?日常生活でうつる確率と気をつけるべきこと
B型肝炎はうつる?日常生活でうつる確率と気をつけるべきこと

目次
B型肝炎とは?
B型肝炎とは、B型肝炎ウイルスによって引き起こされる肝臓の病気です。また、B型肝炎ウイルスの感染は、持続感染と一過性感染にわけることができます。
持続感染とは?
持続感染とは、B型肝炎ウイルスが6か月以上に渡り、体内に残っている状態をいいます。一般的には「キャリア」といわれ、日本には、約110~140万人以上いるとされています。
持続感染している人の約80%強は、B型肝炎ウイルスに持続感染しているものの、肝炎を発症していない「無症候性キャリア」です。
ただし、無症候性キャリアのうち、約20%弱が慢性肝炎を発症し、さらに肝硬変や肝臓がんに進行する方は、そのうち年2%といわれています。慢性肝炎は発症すると、主に倦怠感や食欲不振などの症状が出ます。そのような症状が出たら、早めに医療機関で検査を受けましょう。
一過性感染とは?
一過性感染とは、B型肝炎ウイルスに感染した数か月の後に、身体からウイルスを排除し、免疫を獲得した状態をいいます。
一過性感染の場合、約80%は症状が出ないまま自然治癒しますが、約20%の方は、急性肝炎を発症します。急性肝炎を発症した場合、稀に劇症化することもあります。
急性肝炎が発症すると、主に、発熱や倦怠感、食欲不振、嘔吐、黄疸などの症状が出ます。
B型肝炎ウイルスは日常生活でうつる?
B型肝炎ウイルスは、ウイルス感染者の血液や体液に傷口や粘膜などが接触することで感染します。一方で、握手など、単に接触したりすることで感染することはなく、また空気感染や飛沫感染することもないため、一緒に食事を食べたり、入浴することで、感染することはありません。
よって、日常的に気を付けていれば、感染する可能性は低いといえます。
主な感染原因は何?
B型肝炎ウイルスは、血液や体液を介して感染します。具体的には、以下のようなことがあると感染する可能性があります。
母子感染
母子感染とは、B型肝炎ウイルスに持続感染している母親から子どもに感染してしまうことをいい、主に出産時に産道などで感染してしまいます。母親の感染力が強い状態(HBe抗原陽性)であるときに、出産すると、ほぼ100%の確率で子どもに感染し、そのうち、85~90%が持続感染してしまいます。
ただ、1985年から行なわれている「母子感染防止事業」により、現在では、母子感染する可能性はほとんどありません。
集団予防接種等による感染
1948(昭和23)年7月1日~1988(昭和63)年1月27日までの間、各自治体で行なっていた集団予防接種等では、注射器等を交換せず、連続使用していたことにより、B型肝炎ウイルスに持続感染してしまった方が45万人以上いるとされていいます。
なお、上記期間以降は、注射器の使い回しはしないように指導されていますので、予防接種で感染することはありません。
性交渉による感染
成人におけるB型肝炎ウイルスの感染原因として、最も多いのは性交渉による感染です。
成人してからB型肝炎ウイルスに感染した場合、ほとんどの場合は、一過性感染となり、持続感染化することはありませんが、B型肝炎ウイルスのなかには、成人感染しても、持続感染化するウイルス(ジェノタイプAe)があり、その場合は、約10%は持続感染します。
血液が付着したものを共有することによる感染
B型肝炎ウイルスの持続感染している人が使用したカミソリや歯ブラシなどを共有することにより、感染する可能性があります。
また、入れ墨やピアスで使用する器具等に適切な消毒などがされていないと、感染する可能性もありますので、注意が必要です。
その他、薬物犯罪(覚せい剤など)で、注射器を使いまわすことで感染することもあります。
B型肝炎ウイルスの感染防止策
上述したとおり、日常生活を行なう上でB型肝炎ウイルスに感染する可能性は低いですが、感染しないようにするためには、以下のことに気を付けておく必要があります。
- カミソリや歯ブラシなどを他人と共有しない。
- 血液や体液が付いたものは、他人に触れることのないように、適切に処理する。
- 性行為のときには避妊具を付け、不特定多数の方と性交渉をしない。
- 乳幼児に、口移しで食べ物等を与えない。
B型肝炎ウイルスの検査について
もし、B型肝炎ウイルスに感染しているかどうか不安がある場合、まずは肝炎ウイルス検査をすることをおすすめします。
検査の結果、持続感染している場合は、症状がなくても、今後、慢性肝炎などが発症する可能性があります。そのため、ご本人が専門医療機関を受診する必要があります。また、他人に感染させてしまう可能性もあるので、家族やパートナーなどがB型肝炎ワクチンを接種するといった対策が必要となります。
B型肝炎給付金対象者について
B型肝炎ウイルスに持続感染しており、生年月日(1941年7月2日~1988年1月27日)が対象となる方のうち、以下の要件を満たしている場合、給付金を受け取れる可能性があります。
給付金額は病態により50万円~3600万円が支給されます。
【要件】
- B型肝炎ウイルスに持続感染していること
- 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること
- 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
- 母子感染でないこと
- その他集団予防接種等以外の感染原因(父子感染、成人感染、輸血や医療行為での感染等)がないこと
弁護士に依頼するメリット
もしB型肝炎給付金請求の対象となる場合、手続きは本人でも行なうことができますが、医療記録の取り寄せや裁判所への出頭など、面倒なことが多くあります。弁護士に依頼することにより、手続きをスムーズに行なうことができます。
B型肝炎はうつる?日常生活でうつる確率と気をつけるべきこと まとめ
-
B型肝炎ウイルスの持続感染とは?持続感染とは、B型肝炎ウイルスが6か月以上に渡り、体内に残っている状態をいいます。
-
B型肝炎ウイルスは日常生活でうつる?B型肝炎ウイルスは、ウイルス感染者の血液や体液に傷口や粘膜などが接触することで感染します。一方で、握手など、単に接触したりすることで感染することはなく、また空気感染や飛沫感染することもないため、日常的に気を付けていれば、感染する可能性は低いといえます。
-
B型肝炎ウイルスの主な感染原因は何?母子感染、集団予防接種等による感染、性交渉による感染、血液が付着したものを共有することによる感染などが挙げられます。
同じカテゴリーの記事一覧
-
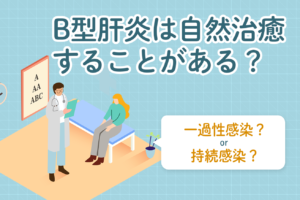 B型肝炎は自然治癒することがある?病院で血液検査をしたところ、「B型肝炎になったことがあるけど、もう治っている」と言われることがあります。ここでは、B型肝…
B型肝炎は自然治癒することがある?病院で血液検査をしたところ、「B型肝炎になったことがあるけど、もう治っている」と言われることがあります。ここでは、B型肝… -
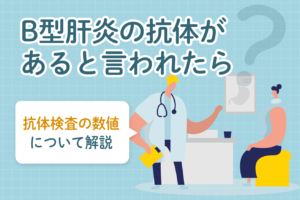 B型肝炎の抗体があると言われたらどうすればいい?抗体検査の数値について解説病院や健康診断などで血液検査を行なった結果、「B型肝炎の抗体がある」とか「過去に感染した跡がある」と言われることがありま…
B型肝炎の抗体があると言われたらどうすればいい?抗体検査の数値について解説病院や健康診断などで血液検査を行なった結果、「B型肝炎の抗体がある」とか「過去に感染した跡がある」と言われることがありま… -
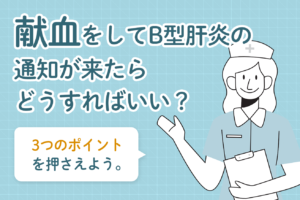 献血をしてB型肝炎の通知が来たらどうすればいい?献血をした結果、感染症検査に異常がみられると、日本赤十字社から封書でお知らせが届きます。ここでは、通知を受け取った後どう…
献血をしてB型肝炎の通知が来たらどうすればいい?献血をした結果、感染症検査に異常がみられると、日本赤十字社から封書でお知らせが届きます。ここでは、通知を受け取った後どう… -
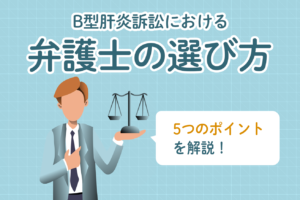
- 請求について
B型肝炎訴訟における弁護士の選び方とは?弁護士を選ぶ5つのポイントB型肝炎給付金における法律事務所(弁護士)の選び方、そのポイントについて説明していきます。 -
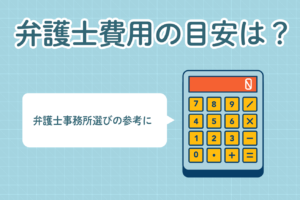
- 請求について
B型肝炎給付金で弁護士費用はどれくらいかかる?その目安とはここでは、B型肝炎訴訟の弁護士費用の仕組みと目安について説明します。弁護士費用についての知識があれば、弁護士事務所を選ぶ… -
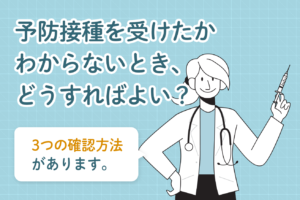
- 対象者について
B型肝炎給付金で予防接種を受けたかわからないとき、どうすればよい?B型肝炎ウイルスに持続感染していたとしても、集団予防接種等を受けていることが証明でないと給付金を受け取ることはできません… -
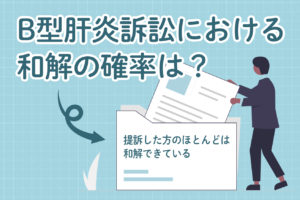
- 請求について
B型肝炎訴訟における和解の確率を知りたい。目安となる数字とは?相談者の中には、「国と和解できる確率が高いなら、手続きしてみようかな」という方がおられます。ここでは、訴訟した方のうち、… -
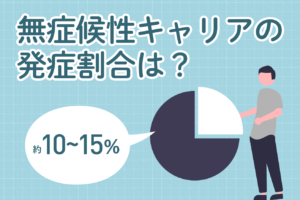
- 対象者について
B型肝炎で無症候性キャリアの場合、どれくらいが発症する?B型肝炎に持続感染していても、肝炎を発症していない方を「無症候性キャリア」といいます。ここでは、無症候性キャリアについて… -
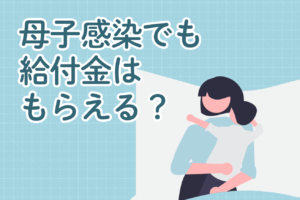
- 対象者について
B型肝炎の二次感染についてB型肝炎ウイルスが母親から感染し、母親が集団予防接種等を原因としてB型肝炎ウイルスに持続感染していた場合、二次感染者とし… -
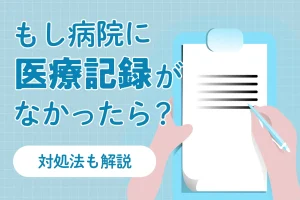
- 請求について
B型肝炎給付金請求に必要なカルテがない場合どうしたらいい?手続きに必要な医療記録(カルテや検査記録等)の説明や、医療記録などが現存していなかった場合ついて、詳しくご説明します。